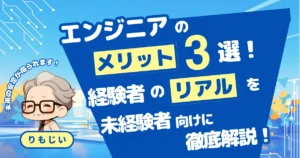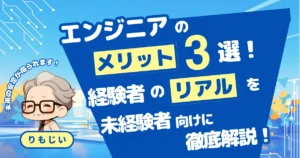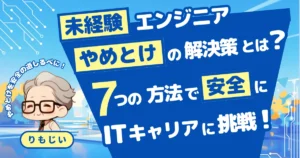未経験からでも IT エンジニアになれる? それって本当に現実的なの?
未経験から IT 業界への転職は、様々な情報が錯綜していて心配かもしれませんね。わたし自身も IT エンジニアになる際は先行きの不透明さから不安でした。
しかし、その不安や心配は大切なサインです。わたしの 20 年の IT エンジニア経験を鑑みても、安心して IT キャリアを歩むためには押さえておいた方が良い大事なポイントがあります。
この記事ではまず、未経験の方が不安に感じる理由の候補 7 つを明らかにします。その上で、それらの不安を安心に変え、現実の壁を乗り越えるロードマップをお伝えします。
この記事を読むことで、あなたは IT キャリアへの不安を払拭する術を知ることができます。安心して次へのアクションを始められるようになりますよ!


- IT 歴 20 年のエンジニア
- 大学、研究所、自社開発企業でプログラミング、サーバ、ネットワーク、クラウド、社内情シスなどの多種の業務を経験
- 安定志向な性格で安心や安全が大好き
- 未経験者向けに 安定志向の IT キャリア入門 で情報発信(お休み中)
- 現在は note で「もやさんの人生らくになるラボ」 を運営中
- エンジニアに興味がある人に安心して IT キャリアを歩んでほしい!
エンジニア未経験者が直面する 7 つの現実の壁


はじめに IT キャリアに対して感じる不安について、りもじい自身の経験から 7 つの理由に分類してみます。
不明確な IT エンジニアの役割
IT エンジニアに求められることってなんでしょう?
必要な技能としてプログラミングはよく挙げられますね。確かに IT 技術者としてコンピュータを操作するプログラムを扱えることは重要な技能です。
しかし、「プログラムが書けること」が IT エンジニアの役割の全てではありません。新しい技術が出てくるたびに「これからは 〇〇 の時代で、プログラマーやエンジニアは不要」なんて煽り文句はよく出てきます。こういった言葉でグラッと不安を感じてしまうと、ITキャリアを安心して歩めませんよね。
分かりにくい IT 業界の構造
IT 業界がどのようなビジネスモデルで成り立っているんでしょう?
キャリアチェンジを検討する際に『IT エンジニアなら年収 〇〇 は期待できる』といった言葉はよく見ますよね。ですが、その年収はどのように生み出されているのでしょう。あなたが会社にどのような貢献をもたらすことで適正に年収が得られるのでしょうか。
報酬の源泉がどこにあるのか分からないままキャリアアップを目指すのは、不安定なキャリア形成となる恐れがありそうです。



ちなみに私は、これを見誤って転職後 4 ヶ月でリストラにあった経験があります…。
何から学べば良いか分からない IT 技術
IT 技術を何から学べばよいか自信は持ててますか?
学ぶべきとよく挙げられるプログラミングだけでも、言語としてかなりの数の選択肢があります。その他にもデータベースやネットワーク、セキュリティなど重要な技術は数多くあります。
自分が目指すキャリアにとって、学ぼうとしていることが最適であると確信がないと不安にかられますよね。
常に求められる IT 学習
IT 学習を継続できるイメージはありますか?
IT 分野の進歩は早いので、継続的な学習は必須であるとよく言われます。私自身も IT に 20 年関わってきて、かつて手作業で時間を掛けていたものをコンピュータが代わりにサクッとやってくれるようになったという経験もあります。継続的学習の必要性は、りもじいも実感しています。
一方で、継続的な学習って辛い、というイメージはありませんか?辛いことを続けるキャリアはあまり幸せにはなれなさそうですよね。
IT エンジニア評価の不透明さ
IT エンジニアはチームや会社から何を基準に評価されるのでしょう?
例えばプログラマーなら何で評価されるのでしょうか。プログラムしたソースコードの量でしょうか、バグの数でしょうか、もしくは仕上げるまでにかかった時間でしょうか。それとも何か違う基準があるのでしょうか。
この基準がよく分からないと、何のために IT エンジニアとして仕事をしているのかフォーカスがぼやけ、先行きが不透明で不安になってしまいますよね。
人生をデザインする経験の不足
IT キャリアを歩んだ先で自分が何を求めているのかイメージは持てていますか?
IT エンジニアに興味をもったことは素晴らしいことです。でも、なぜそのような興味を持たれたのでしょうか。 IT 技術は広く深いですし、その技術を扱う力量のある人材はこれからも多くの人や会社が欲しがります。そのため、一定のレベルに達すると人生は安定度は高まります。
でも、そもそもなぜ IT キャリアを歩みたいと思ったのか、その初心を見失っていると、自分の人生が望まざる方向へと徐々に進んでいってしまいます。「気がついたら見知らぬ場所にいた」なんて事になると怖いですよね。



私はこの意識が足りなかったおかげで、仕事も家庭も上手くいっているはずが、長年かけて望む人生からジワジワと遠ざかるハメになりました。
実力にそぐわない場での苦戦
IT キャリアのスタート地点は実力に見合っていますか?
IT 人材はたいていはどこでも不足しているため、未経験でも意欲があれば就職できる可能性はあります。
しかし、その場所でどのように活躍できるのか、具体的に想像できているでしょうか。
新しいステージに活躍の場を求める際は、チャレンジ要素はあった方が良いと思います。しかしそれ以上に、その場所に今の自分が求められるという大前提があるはずです。
そのような前提がなく、活躍できるかが分からない場所から IT キャリアを始めるのは不安が大きいですよね。



IT キャリアに興味はあるけど不安…、という方の不安要素を経験をもとに整理してみました。当てはまるものはありましたか? 次にこれらの不安を安心に変える方法をお伝えしていきますね。
未経験から安心して IT キャリアを始めるための 7 ステップ
ここからは、現実の壁を乗り越えるためのロードマップ 7 ステップをご紹介します。
IT エンジニアへの期待を客観的に理解


IT エンジニアに期待されることは、① IT の知識や IT 技術といった専門性を持つ人ならではの解決策によって、② 人や組織の課題を解決すること、であるとわたしは考えます。
① はなんとなくイメージがつくかもしれませんが、 ② は相手が必要ですよね。
例えば、自分が研究所に勤めていた際には、取引先の IT 企業のエンジニアの方々は、研究者をお客さんとして、次のような役割も担っていました。
- 研究者が期待するシステムに関するヒアリングや具体化
- システム開発に必要な工程の洗い出し
- システム開発のスケジュール管理
この時の ② は、研究者による研究活動のサポートをすることでした。研究者は目的はイメージできていても、どのようなシステムがそれに適しているのか、また作ることが現実的であるのか、そしてそこに至るスケジュールの管理については詳しいわけではありません。そこをエンジニアが埋める形で役割を果たしていました。
その後勤めた自社開発企業では、IT エンジニアでも立場に応じて ①、② は違っていました。イメージが付きやすいよう、以下に例を挙げてみました (実際にあった事例というわけでありません)。
| ② 解決すべき問題の例 | ① IT による解決策の例 | |
|---|---|---|
| プロダクトマネージャー | 世間的に話題に上がるようになったセキュリティ問題についての利用者からの疑念の発生 | 問題に関する情報収集とプロダクトとしてのセキュリティ対策方針の表明 |
| 開発リーダー | 使用されるプログラミング言語起因での開発スピードの低下 | 新規言語の調査と選定、言語切替の計画立案、計画の管理 |
| 開発メンバー | プロダクトの機能の不足や老朽化 | プログラミング能力の提供による機能開発や改修 |
なお、組織の上位の立場になってくると、問題の解決策として IT の知識や技術に依らない選択肢も取れることがあります。こういった面から管理職は IT エンジニアとは別、という見方もあります。しかし、わたしの経験上、IT エンジニアの仕事の問題解決は IT について一定の経験や知識がある人の方が深く問題を理解し、その分効果的な解決策を提示できる場合が多いと感じています。そのため、そのような立場の人もひっくるめてここでは「IT エンジニア」と表現しています。
ちなみに、上記の例は自社開発企業だからこう、というわけではなく、組織の体制やエンジニアの人数によって自分やチームが向き合う相手は誰か、つまりは ② も変わります。それに求められる ① も変わるというわけですね。
優れた IT エンジニアとして安定していくには、次のことを併せて進めていくことが大切です。
- 世の中で IT により解決できそうな問題にどういうものがあるかを知る
- 解決策としての IT の技術や知識を深める



こちらの記事ではりもじいが経験した職種を中心に、 IT エンジニアの種類ごとにその魅力やオススメな人を紹介しています。実体験を元にしており、IT キャリアのリアルを知りたい方には参考になると思います。ぜひチェックしてみてくださいね!
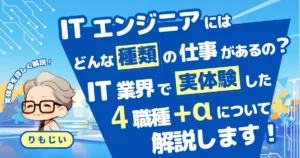
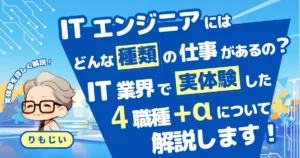
IT 業界の多様なビジネスモデルの把握


IT 業界と一口に言っても、実際には様々なビジネスモデルに基づいた IT 企業があります。それらは時に競争し、また時に協力し合ってビジネスの成長を目指しています。
ここでは一例として、サブスクリプションモデルのサービスと買い切りモデルの製品を販売する企業のビジネスモデルと、そこでの IT エンジニアへの報酬はどのように生み出されているかを解説します。
その解説の前に、そのようなサービスや製品を作って販売する企業における IT エンジニアの報酬の一般的な構造を説明します。IT エンジニアの報酬はサービスや製品の販売で得られた収入が源泉となります。すごくざっくりと表現すると、このような式になるわけですね。
IT エンジニア A さんの報酬 = サービスや製品の販売収入 − サービス・製品の開発費用 − 販売に使う費用 − 会社の維持やその他いろいろな費用 − Aさん以外の人に対しての報酬
サービスや製品を作る立場の A さんが多くの報酬を得るためには、次のいずれかの影響を及ぼせると良さそうです。
- 「サービスや製品の販売収入」を増やす
- 「サービス・製品の開発費用」を減らす
サブスクリプションモデルと買い切りモデルの特徴と、a, b へ影響を及ぼすためにできることを挙げると次のようになりそうですね。
| サブスクリプションモデル | 買い切りモデル | |
|---|---|---|
| 利用料の特徴 | 定期的に少額の利用料が発生 | 初期にのみ大きな利用料が発生 |
| サービス・製品の特徴 | 継続的なアップデートや変更を前提とする | 不具合の解消を除き変更は限定的 |
| 他社への乗り換え | 定額のため契約解除して乗り換えるのも簡単 | 初期投資が大きく変更が困難 |
| a の方法の例 | 顧客満足度を高めるための、新機能追加や改修のリリースサイクル高速化 | 製品の初期品質を高めるための徹底した品質管理とバグの排除 |
| b の方法の例 | システムのコストの分析と最適化 | 製品リリースまでの開発コストを抑えるための厳密な開発計画の策定とプロジェクト管理 |
なお、ここでは単純化した例を挙げましたが、実際にはこれら両方を扱う企業もあったりします。またそれぞれのモデルでも、サービスや製品が成長期でどんどんお客さんを増やしているフェーズのものか、成熟期になってすでに多くのお客さんはいるもののあまり伸びてはいないものか、でも異なってきます。
ちなみに「Aさん以外の人に対しての報酬」に対して相対的に A さんの報酬の割合を増やす、という手段もありますね。企業から見れば、 a, b に対しての大きなインパクトを及ぼせる人に対して割合を増やすのが合理的です。これが、昇給や昇進を通じて給与を増やす(=分け前の割合を増やす)、ということですね。
IT エンジニアの年収の相場は、このような実態について、ざっくりと平均をとって得られたものです。目安としては有効ですが、これだけを参考にすると、「未経験スタートの IT エンジニアの給与は安すぎる」と感じてしまいガッカリすることもあるかもしれません。逆に豊富な技術と経験を身につけてもそれに見合わない報酬しか得られない、といったこともありうるでしょう。
IT 業界や IT 企業の実態の理解を深めていけば、IT エンジニアとして果たすべき役割と得るべき報酬も徐々にイメージできてくるようになります。現在の自分は IT エンジニアとしてどれだけの価値提供ができるのか、IT エンジニアというラベルに頼らずにイメージできれば、IT キャリアはさらに安全なものになります。



IT エンジニアの年収がどのように決まるのか、また給料を増やすにはどうしたら良いのかを具体的に知りたい方はこちらの記事も参考にして下さいね!
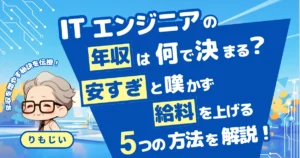
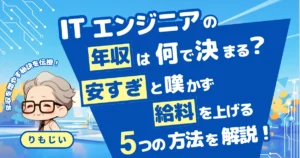



「でもIT業界やめとけって声も聞くよ?」と不安な方は、こちらの記事もぜひ読んでみてくださいね。実は未経験者にも魅力的な、IT業界の 5 つの特徴をお伝えしています。IT業界の歩き方が分かり、安心して挑戦できるようになりますよ!
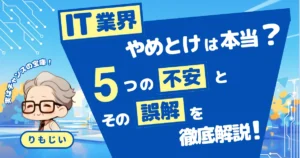
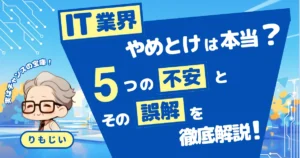
未知の IT 技術が近くにあることを知っておく


IT 技術はたいへん多岐にわたるようになり、それぞれに深堀りされていて全てを個人で熟知するのは無理でしょう、というのがわたしの見解です。
わたしにも次のような経験があり、それなりに色々やってきたようにも思います。
- プログラミング
-
Fortran によるシミュレーションモデル開発、Ruby でのコード解析ツール開発、Python での運用管理ツール開発など
- サーバ管理
-
Linux OS や Windows OS のセットアップ、メンテナンス、トラブル対応
- ネットワーク管理
-
自社開発 Web サービスを支えるネットワークのセットアップ、メンテナンス、トラブル対応
- クラウドの活用
-
クラウドサービス (AWS、GCP など) の導入や管理
- 社内情報システムの管理
-
IT 企業の業務を支える基幹システムのセットアップやメンテナンス、スタッフの PC のトラブル対応など
それでいて、今の自分がエンジニア個人として任されても難しいなと思うものもたくさんあります。色々あり過ぎますが一部を挙げると次のようなものです。
- アプリ開発
-
現代的なアプローチで実用的なアプリケーションを開発するには、プログラミング言語はもとより、開発フレームワークなど様々なライブラリやツールに関する技術も必要
- 人工知能 (AI) の技術を応用したシステム構築
-
機械学習やディープラーニングなどの専門的な知識が必要
- IoT 技術の活用
-
家電製品やウェアラブルデバイスなどのデバイス制御やデータ処理に IoT 向けのプログラミングやハードウェアの知識が必要
- 仮想現実(VR)や拡張現実(AR)の活用
-
高度なグラフィックス処理、ユーザーインターフェースの設計、リアルタイム性の確保など多くの技術的課題を解決する技術と経験が必要
正直なところ、これからこれらを全部学んでいこうという気は全然ありません。従って、人気のある何かの技術からとにかく学び始めようというスタンスには賛成です。わたしなどは人気、以前になんとなく面白そうなものから取り組んでしまったぐらいの人間ですしね。
未経験から始める際のアプローチとして、例えば学習コンテンツが多く学びやすいプログラミング言語から学び始めることも選択肢として良いものだと思っています。一方で、そのプログラミング言語がどれだけ推されている素晴らしいものであっても、「その技術一本だけでどうにかしよう」と思ってしまうとその先はなかなかハードです。
データを整合的に管理するならリレーショナル・データベースに任せてしまう方が楽ですし、ハードウェアの故障の対策であればサーバやネットワーク側で対処してしまうのが一般的です。セキュリティの対策もプログラムだけではなく、専用の機器やサービスなどと組み合わせて対処する場合が多いです。
数多くの技術領域があるのは、それだけ現実の問題に対処するのに適した方法は様々にあるということなんですね。
ざっくりとでも、どの IT 技術が何のために編み出され、どういった問題解決に対して用いられるのかを知ること、ないしはそれを知る術を身に着けておくことをオススメします。それにより今取り組んでいる IT 技術により安心して集中できるようになります。
また、分かりやすさから「〇〇エンジニア」という言葉も多いですが、この言葉に引きずられて技術領域を自分で限定してしまわないことも大事です。あくまで今の自分が持っている、またはこれから目指す主要技術を示す、ぐらいで考えておくのが良い思います。ちょっと視野を広げて手を伸ばすことで、意外と簡単に目の前の問題を解決する術が得られたりしますからね。



いまや IT という言葉も様々な意味合いで使われるため、そもそも IT ってなんなんだろう? という方もいらっしゃるかもしれませんね。そのような方向けに IT の基礎を分かりやすくまとめた記事も用意しています。ぜひ読んでいってくださいね!
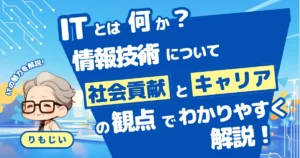
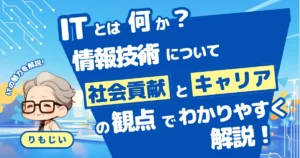
興味と安心感による継続的な IT 学習


IT 学習について、わたし自身は次のような両極端な時期がありました。
- 「すごく面白い!」と感じて能動的に学んでいた時期
- いよいよ必要になるまでは学ばない受動的な時期
そんな自身の経験を分析し、継続的な学習に必要なものが何かを解説します。
まず、学習といっても人によってイメージがバラバラだと思います。ここでは、学習は以下のようなものだとします。
学習 = 変化する周囲の環境に適用して生き抜くために、必要な知識やスキルを身につける行動
このように定義できるとするなら、本来は学習すればするほど安心できるはずです。わたしのように安定志向な人ならさらに意欲が出そうなものです。なぜしんどく感じたり、面倒でやらなくなってしまうのでしょう。
自分の過去の経験に当てはめると、次のような状況で無理に学ぼうとし、結果的に学習を避けるようになってしまったと分析しています。
- 取り組む学習が自分にどう役に立つかイメージできていない
-
知識の暗記になっているパターンでした。イマドキは標準的な知識は AI が教えてくれてしまいますし、この手の「学習」への意欲を保つのは難しいですね。
- 理解できない内容を無理に学ぼうとしている
-
高度な知識を活用できるものとして吸収するには、そのための土台となる知識や経験が必要です。「よく分からないな」と感じたらあまり頑張って学ぼうとせず、さっと撤退してしまいましょう。いずれスッと理解できるようになりますので。
- 自分自身や周りの状況をどう改善したいかイメージできない
-
現状をこう変えていきたいな、というポジティブな意欲が湧かない状況では、学習のモチベーションを高めるのは難しいですよね。
- 心身が疲労している
-
疲れている時は休息や栄養補給が第一です。知識を頭に入れるのはある程度元気がある状態で取り組みましょう
- 睡眠不足
-
寝ましょう
わたしは一時はかなりこじらせて、「自分は学ぶことができない人間だ」とまで思い込む始末でしたが、上のような状況を整理して学ぶスタンスを改めることで、学習の面白さを再度感じることができるようになりました。
わたし個人は、覚悟と根性では学び続けることはできない人間です。多くの方も似たようなものではないかなぁと感じています。ただ本来は生存確率を高めるという原始的な欲求のために望んで学ぶという状況があったわけで、覚悟や根性という高度な精神力はなくてもよいはずなんですよね。
IT 学習についても、環境を整え、学習へのスタンスを適切にすることで自然と続けていける状況は作ることができます。「継続的な学習は辛い」と感じる方は自分がダメだと責めるのではなく、辛いと感じる理由を客観的に分析してみましょう。



プログラミングの独学に不安を感じる方はこちらの記事もぜひ読んでみて下さい。独学成功の秘訣である目標設定の仕方や実践的な学習プランについて紹介しています!
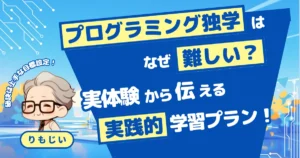
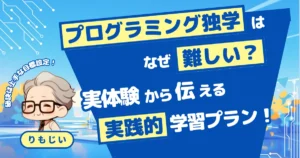



IT 学習について続けられるか不安な方はこちらの記事もぜひ参考にしてくださいね!新人エンジニアでもモチベーションを高く維持しながら効率的に学ぶ実践的な方法を紹介しています。
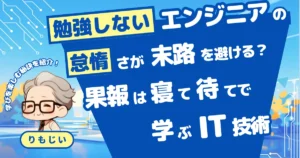
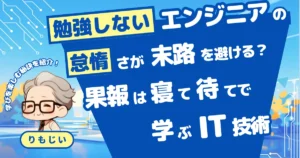
デキる人の行動を真似て評価基準を体得する


IT エンジニアの評価はどの組織でも試行錯誤が続けられてる問題です。わたしは、この難しさは主に次の 2 つに起因して、評価の公平性をスッキリとは示しにくい点にあると考えています。
- スキルセットの多様性が評価軸の複雑化を招く
- IT のスキルセットは大きく分類するだけでも 10 種類を超え、さらに実践的な技能という点ではもっと細かくなります (参考: IT スキル標準 | IPA、IPA 試験区分)。
- エンジニア個々人がこれらの IT 技術を各々バラバラに習得していくことが多く、公平な評価軸を作るのはなかなかハードです。
- 共同作業に伴って個々の貢献度が見えづらい
- 実際の IT 企業では1人のエンジニアが全ての業務を完結することは少なく、複数のメンバーで協力して業務を担う場合が大半です。
- 1つの成果に対して誰がどのように貢献して結果を出したのか、チームの外からでは見えにくい場合があり、公平性に疑念が生じる場合もあります。
この問題は根本的な解決は当分難しいと思うので、IT キャリアに興味がある方には次のアプローチを採ってもらうことをオススメします。
- 既に組織で評価されている人の行動について情報収集する
- 可能なことから真似てみる
初めからその組織で評価されるポイントを論理的に分析するのは難しいと思うので、先輩の技を盗むというアプローチですね。
実際にその企業で働く前であっても、面接や面談の場が得られれば、現場のエンジニアや管理職の人と会話する機会もあるかと思います。その際に A を行うだけでも、公式の評価ルールでは表現しきれないチームで大切にしていることを知ることができるかもしれません。
一括りに IT エンジニアと言っても、仕事をする上で大切にできるポイントは様々あり、組織やチームで何が重視されるかも異なりますからね。
- プログラムの知識量やコードの効率的に書く能力
- システムの設計能力
- セキュリティへの理解と対策の能力
- サービスの品質管理能力
- 論理的に人に伝える能力
- 相手の気持ちを共感する能力
- 人の言葉に素早く反応する能力
- 新しい技術を素早く取り入れる能力
- 1つの技術を深く理解する能力
- などなど
多くの企業は貴重な IT エンジニアを大切にしたいと思っています。適切で公平に評価したい想いもあります。しかし IT エンジニアの特性上、それを完全に言語化してルールにまで落とし込む事ができている組織は少ないのではないかとも感じています。
先輩たちの行動を参考にして自ら何が有効な評価軸であるか情報収集し、実際に真似するという行動で評価軸を体得していきましょう。チームや組織で適切に評価されれば、IT キャリアを安全に始める近道になっていきます。



なお、評価の難しさに加え、未経験からエンジニアを挑戦する人にとって、人間関係や仕事の内容がきついのでは?と不安な方もいらっしゃるかと思います。こちらの記事ではりもじいにとってのきつかったリアルな体験と、未経験からエンジニアに挑戦する人がきつい状況を乗り越える方法を解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてくださいね!
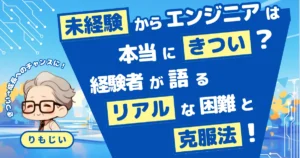
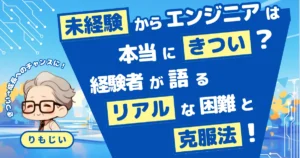



周りから評価されるには情報収集と行動の両輪がカギになりますね。面接の場を情報収集の機会と考えれば、企業で働く前であっても高く評価されるための下準備が進められます。
面接が不安…、という方はぜひ次の記事をご覧ください。未経験者が IT 面接に成功するための実践的方法を紹介しています!
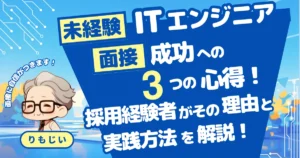
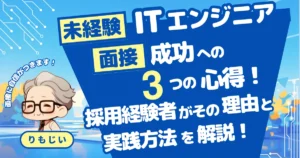
キャリアビジョンを意識した IT キャリア選択


いい大学からいい会社へ、そこでしっかり勤め上げて退職金と年金で金銭的不安のない悠々自適な老後生活へ、というのは何となくわたしがイメージしていた、高度経済成長期の一般的、または模範的なキャリアビジョンだったのかなと思います。
今は企業にもそこで働く人にもより多くの変化が求められるようになりました。また人生 100 年時代などと呼ばれるような超高齢社会では、ある会社を退職した後も「余生」ではなく、積極的な社会的な活動が必要、といった考えも出てきています。
そこにきて、幸福についても多義的になっています。これはかつては新聞やテレビという一方向のメディアが主流であったのに対し、今は SNS によって誰しもが双方向で発信できるようになり、数多くの「幸せの形」が示されたり、それに対する反応が共感できる環境が整ったことが関係しているのでしょう。
パッと思いつくだけでも、幸福を感じ方は様々です。
- 家族や友人との円満な関係
- 仕事の達成感
- 趣味の充実
- 経済的な安定
- 健康的な生活
- 社会的な貢献
何を大切にするか、その組み合わせは人それぞれです。近い感性の人はいたとしても、全く同じということはないでしょう。
安心してITキャリアを歩むための7ステップにこの話を入れたのは自らの経験に基づいています。
多様性のあるITエンジニアという職種において、どのように働くのか、また何を目指していくのかは自らのキャリアビジョンとも密接関わることになります。
- 経済的な安定を重視
-
経済基盤が大きい大企業が重視するスキル、例えばITプロジェクトのマネジメントの専門性を高めるキャリアを選択する
- 社会的な貢献を重視
-
新しい IT 技術を早くに取り入れて活用できる腕を磨き、特定の社会課題の解決を目的とするスタートアップ企業で活躍する
- 仕事の達成感を重視
-
要件定義からプログラミングまで幅広く技能と経験を身につけ、少数精鋭の企業でプロジェクトの上流から下流まで熟知できる環境を獲得する
ここで挙げたことは単純化した一つの例です。ここで挙げた「仕事の達成感を重視」についても、深掘りすれば人によって十人十色でしょう。
- 自己成長が達成感を満たす場合
-
自分にとって新しい力を身につけることが達成感の源泉であれば、仕事は同じことの繰り返しではなく、新しい取り組みが必要になります。
- チームとの深いつながりが達成感を満たす場合
-
一緒に仕事をする人との新しいつながりやより深いつながりが達成感の源泉という場合もあるでしょう。この場合はプロジェクトごとに関わる人やその関係性に変化があった方が達成感は生まれやすそうですね。
初めから自分が望む事を明確にできる人は意外に少ないのではないでしょうか。経験で自らの新たな面を知り、自分が何を大切に思うのかが深掘りされていきます。
自分が大切なものを大切にしやすい方向性は何か、定期的に意識して見直すことで、ITキャリアは自分を望む人生へと近づけてくれるようになります。



キャリアビジョンがうまく描けないな、という時はこちらの記事を参考に志望動機を作ってみるのも良いですね。あなたのこれまでの歩みと、これから望む未来を具体的に形にすることで、あなたにとって大切なことが浮き彫りになります。AI の活用で効率的に作れるようにもなるので、ぜひ取り組んでみて下さい!
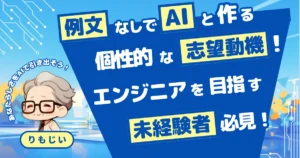
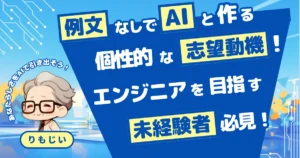



これまでの話を踏まえて、ITキャリアで後悔しないための具体的な対策についても知っておくと安心です。次の記事では、ITエンジニアとしてのキャリアを歩む中で遭遇する可能性のある後悔とその対策について詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてくださいね!
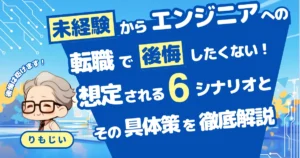
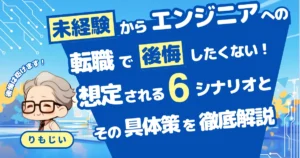
すぐ役立てることも就職先選定の条件に


新たなキャリアを選ぶ時は様々な条件を総合的に、また慎重に選ぶ方が多いのではないでしょうか。
- 年収
- 職種
- 企業の規模
- 福利厚生
- などなど
これらに加え、キャリアチェンジする際には、転職先の教育体制を気にする方も多いと思います。
「一から十まで独学しなさい」と言われるよりは、何を学ぶべきか指針を示してもらえたり、分からないことを丁寧にサポートしてもらえる方が安心ですよね。
教育体制はもちろんあるに越したことは無いのですが、経験的には万人を短時間で一人前の IT エンジニアに育られるような素晴らしい教育カリキュラムを組むのは難しい、と考えています。
もちろん不可能ですと豪語するつもりはないです。そういったものができたら素晴らしいですしね。ただ、IT エンジニアのリソースはどこでも貴重です。教育はそこそこに、事業の成長に直接寄与することを重視させる場合の方が多いでしょう。
では、ITキャリアを選ぶ方はどうすると良いでしょうか。
わたしの場合、IT 業務かどうかにこだわらず、何か周りの役に立つ事を取り組むことを重視しました。
研究所に技術サポートの立場で勤め始めた際、上司の部屋に散乱していたダンボールを片付けた際は上司だけでなく同僚たちにも意外に感謝されました。
それとメモる事が好きな人間なので、頼まれなくても勝手に自分向けのプチ議事録を作って、相手に「あくまでメモですけど」とシェアすると喜んでもらえました。
もちろんこれらはあくまでも「とっかかり」であり、これだけやっていても IT キャリアは前に進みません。
しかし、IT エンジニアをゼロからスタートする場合、技術者として貢献ができるようになるまで時間がかかる場合はあります。これは本人の成長スピードだけでなく、IT チームが求める技術の特性やレベルにも依存しており、事前予測は難しいものです。
そのような状況でも、何らかの形で貢献して周囲から感謝されていれば、安心して技術を学び IT 業務を身につける事ができます。万が一どうにも自分に技術者は向かなかった、という場合にも、役立っていることをテコにキャリアチェンジしやすい環境が得られます。
20代以上であれば既に何かの形で社会参加している場合がほとんどでしょう。何かしらの個性も意識できており、得意なこともあるかと思います。新たなキャリアを選ぶ時は様々な条件の中に、すぐに役に立てそうなこと(ITに依らない)が具体的にイメージできるか、といった点も加えてみてはいかがでしょうか。



就職の際に安心して IT キャリアを始めるためのアドバイスをこちらの記事にも載せています。ぜひ読んでみてくださいね!
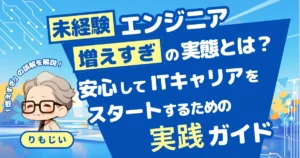
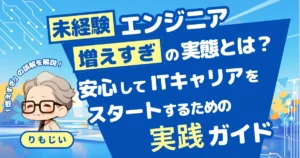
安心してITエンジニアを目指すために今日からできること


さて、ここまでに IT キャリアを挑戦する際に感じる不安な理由を 7 つに整理し、それぞれの対策を解説しました。
わたしの体験に基づく、ある意味では偏見に過ぎないものではありますが、IT キャリアを検討している方の不安の払拭につながるものが何か 1 つでもあったなら嬉しいです。
この記事は不安の理由 7 つの全ての対策をまとめており、それぞれの対策の内容については不足を感じたかもしれません。個別の内容について深掘りしたコンテンツは今後提供予定です。
いま未経験ながら IT キャリアを考えている方は、現状に何かの不安や不満を感じ、新たな道を模索しているのだと思います。
その不安や不満は必ずしもネガティブなものではなく、あなたの人生をより良い方向へと向かせるポジティブなサインと考えることもできます。
このブログでは、IT キャリアへの不安を紐解き、わたしなりの解決策をお伝えしていきます。
このブログを読むことで IT キャリアに前向きになり、学習、情報収集、思索、相談、求職など、さらなる行動につながる方が増えれば幸いです!



ここまで読んでいただきありがとうございました! 安心して IT キャリアを目指せる人が 1 人でも増えてくれれば嬉しいです!
IT エンジニアへの道は厳しい、と言われることもありますが、実は安全なルートもちゃんとあります。こちらの記事では、学習、年収、成長の 3 つの観点で安心して IT キャリアを歩む方法を紹介しています。ぜひ参考にしてみてくださいね!
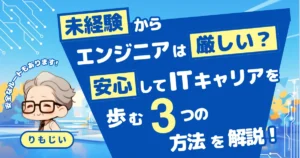
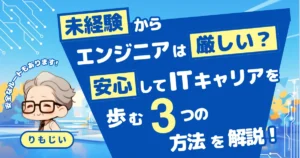



IT エンジニアはあなたの未来に安定をもたらすメリットの多い職業でもあります。りもじいの実体験として得られたメリットを次の記事にまとめているので、こちらもぜひ読んでみて下さいね!